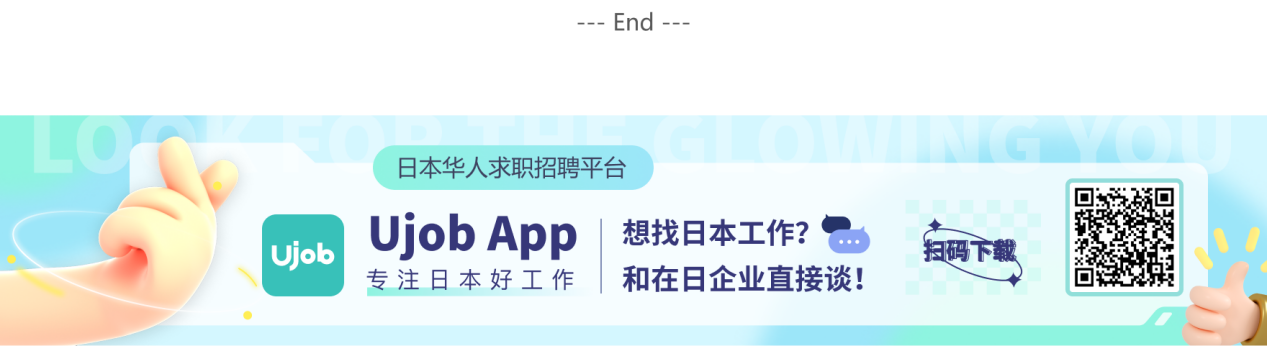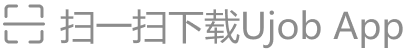毎年3月末から4月初めにかけて、日本各地で桜が一斉に開花し、一年に一度の花見シーズンの幕が開けます。この時期、全国で盛大なお花見イベントが開催され、国内外から多くの観光客が訪れ、淡いピンクの花の海に包まれます。しかし、この美しい伝統が静かに迫る危機に直面していることをご存知でしょうか?老木化が進んだ桜の木のため、一部地域では花見イベントの中止が相次いでいるのです。

日本を代表するソメイヨシノを中心に、儚くも華やかに咲き誇る桜並木。春になれば花見客でにぎわい、写真撮影や宴会が繰り広げられる光景は風物詩となっています。ところが最近、TBSテレビの朝の情報番組が意外な事実を報じました。人々が花見の準備に浮足立つ一方で、各地でイベント中止が相次いでいるというのです。

三重県四日市市の名所「海蔵川の桜まつり」は例年大勢の観光客を集める人気イベントでした。昨年は10万人を動員したこのイベントが、今年は中止に追い込まれました。実行委員会会長は「続けたかったがやむを得ない」と明かします。樹木医の診断で、川沿いの桜の木の老朽化が判明。幹内部の腐食や空洞化が進み、倒木の危険性が指摘されたため、安全を優先した措置でした。



この問題は海蔵川だけにとどまりません。熊本県南阿蘇村の「一心行の大桜」も開花数減少を受けてイベント中止を決断しています。樹木医の勝木俊雄氏は「桜は植えれば永遠に咲き続けると思われがちだが、ソメイヨシノは植栽40年で老木化が始まる」と指摘。手入れ不足で枝折れや枯死が進む現状を危惧しています。

実は現在の桜景観の多くは、戦後の復興期や1980年代の植樹ブームで形成されたもの。40年の時を経て、まさに老齢期を迎えているのです。専門家は「老木の伐採と植え替えが必要」と訴えますが、課題は山積み。多額の費用に加え、高齢化や人手不足がネックになっています。

こうした中、一部自治体ではユニークな対策を開始。IT企業と共同開発した「桜AIカメラ」アプリでは、市民が撮影した画像から桜の健康状態を診断。AIが健康スコアを算出し、自治体が優先対策樹木を把握できる仕組みです。この”市民参加型”の取り組みが、人手不足の解消と保全意識の向上に一役買っています。



近年、中国でも武漢大学や南京鶏鳴寺、無錫鼋頭渚などで桜の名所が人気を集めています。中国の桜は植樹時期が浅く老齢化の危機はまだ先ですが、日本の事例は重要な警鐘と言えるでしょう。

儚い桜の美しさを守るには、持続的な努力が必要です。日本の事例が示すように、自然の景観は当たり前のものではありません。テクノロジーの活用で新たな希望も生まれていますが、この春、桜の下に立つ時、私たちはこう思うかもしれません――この満開の光景は、自然の恵みであると同時に、多くの人々の努力の結晶なのだと。

サクラの花は儚いものですから、今のうちにぜひお花見にお出かけください。この伝統ある春の風物詩が、未来へと受け継がれていくことを願いながら。