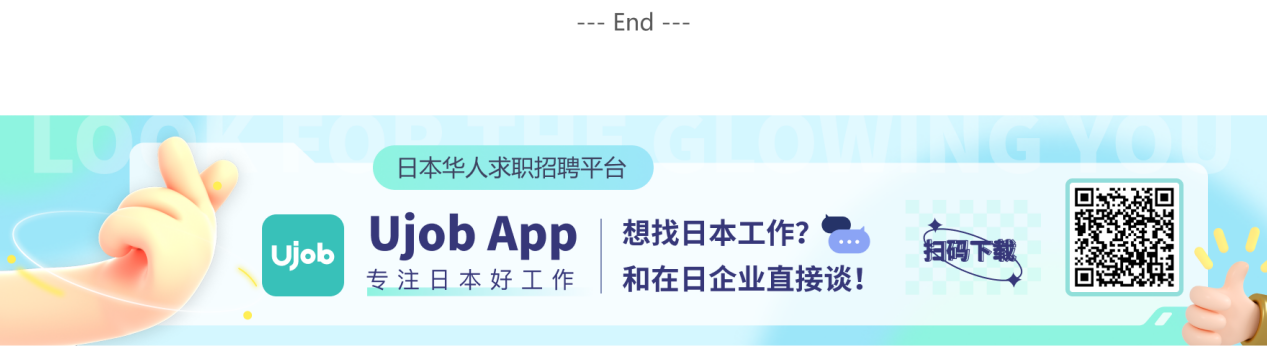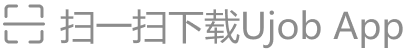多くの中国のネット上で、こんな話が広まっている:『ドラえもん』の未来設定では、のび太は大人になって電気技師になり、日系企業に雇われて蘇州に派遣され、年間200万元(約4000万円)を稼ぎ、「海外出稼ぎ」によって安定した生活を送っているという。

この話はまるで一つのメタファーのようだ:のんびりして何も成し遂げなかったのび太でさえ、結局は海外出稼ぎで生計を立てなければならず、かつて無数の日本の若者の運命を示しているようだ。しかし原作をめくってみると、藤子・F・不二雄の漫画でもアニメ版でも、のび太の未来にそんな描写はない。確かにいくつかの未来設定で「電気技師」になったことはあるが、それは日本国内の小さな企業に勤めており、蘇州の日系企業に赴任したわけではない。

では、この話はどこから来たのか?おそらく二次創作か、ネットユーザーの冗談だろう。しかし興味深いのは、これが全くのデタラメなジョークではなく、現実的な土壌を持っていることだ。

2000年代、確かに大勢の日本の若い技術者が中国の沿海都市に派遣されていた。中国がWTOに加盟した後の10年間、日本製造業の対中投資は急速に拡大し、自動車部品から電子製品まで、パナソニック、シャープからキヤノン、ソニーまで、ほとんどすべての大企業が蘇州、無錫、深圳、天津に工場を持っていた。日本企業は一方で技術を知る人手を大量に必要とし、他方で中国チームとのコミュニケーションを維持する必要があったため、日本の若手社員を中国に派遣することが常態化していた。

日本の若者にとって、これは悪い話ではなかった。海外派遣は往々にして二重の収入を意味したからだ:一つは中国現地での給与、もう一つは日本本社からの手当て。さらに住宅・交通費の補助を加えると、年間数百万円、人民元に換算すれば「年収200万元」という話になる。当時、東京で苦しい生活を送っていた若手サラリーマンが、蘇州や無錫に来ると、突然広々としたアパートと十分な預金を手にし、確かに羨望の的となった。

そこで、こうした実在の歴史的経験をのび太の未来に代入することで、「蘇州版のび太」の説が生まれた。それは原作の設定ではないが、原作よりも時代の気息に近い。
 しかし、過去から現在に目を向けると、微妙なずれに気づく。20年前、日本の若者が生き残るために海を渡らなければならなかったが、今、同じ状況が中国の若者の間で再び起きている。
しかし、過去から現在に目を向けると、微妙なずれに気づく。20年前、日本の若者が生き残るために海を渡らなければならなかったが、今、同じ状況が中国の若者の間で再び起きている。

現在、国内の雇用市場は変化している。高等教育の拡大、経済成長の鈍化、製造業の海外移転により、「仕事探し」が当たり前ではなくなっている。多くの若者が、学歴が低くなくても、国内の主要都市で安定したまともな職を見つけるのが難しいと気づいている。公務員を目指す人もいれば、地方都市で「寝そべり」を選ぶ人もいれば、海外に目を向ける人もいる。

当時の日本人とは異なり、中国は若者の「海外流出」を制限しておらず、留学也好、労働派遣也好、政策的には全体として「行き来自由」だ。本当の障害は、受け入れ国側にある。インドは基本的に中国人にビザを発給せず、ある意味で中国をライバル視している;東南アジアは中国資本と華人商人には開放しているが、一般労働者には就労ビザを出したがらない;欧米の大国はビザ審査を厳しくしており、家や車を持っている中流の親でさえ却保される可能性があり、20代前半の若者なら尚更だ。

こうした環境下で、一部の人は「グレーな道」を選んでいる。観光ビザや親族訪問ビザで先進国に入国し、その後「オーバーステイ」して、飲食業、建設業、介護などの肉体労働に従事する。オーストラリアはよく話題になるが、そこは世界で最も高い最低賃金を誇るからだ。左官、ペンキ職人、タイル職人は、苦労を厭わなければ、5、6年で300万元(約6000万円)を貯めるのは難しくない。最終的に強制送還されても、帰国後は「寝そべり都市」で小さな家を買い、残ったお金でのんびり暮らし、配送や警備の仕事を見つければ、少なくとも飢えることはない。

こうした話は残酷に聞こえるが、現実である。それはかつて日本の若者が中国で働いたことと同じで、全球化の隙間で生き残る方法を探しているのだ。しかし、00年代と比べて、現在の世界環境はすでに異なっている。当時の日本人が中国に来たのは、企業派遣という形で、完備された会社システムとビザのチャネルがあり、収入は高く、リスクは小さかった。しかし現在の中国の若者は個人行動が多く、ビザの制限、身分の不安定さ、法的保護の不足という現実に直面している。一旦問題が起きれば、効果的な支援を得るのは難しい。

だから、「のび太が蘇州で働く」という誤った情報は、単なるジョークではない。それは時代を超えた繰り返しを反映している。ただ、のび太は所詮架空の人物だ。現実の若者にはドラえもんの不思議なポケットも、過去に戻って選択し直せるタイムマシンもない。彼らが頼れるのは、自分の勇気と粘り強さだけだ。これこそが「蘇州ののび太」の真の寓意なのかもしれない:若者に選択肢がほとんどない時代において、海外出稼ぎはやむを得ない選択であると同時に、もう一つの生き残り方なのである。

人はどうにかして生きていかねばならず、自分自身のために明日を図らねばならない。そしてこうした全球化の繰り返しは、今後数十年間、恐らく絶えず現れ続けるだろう。